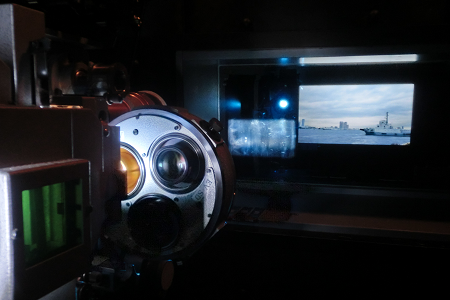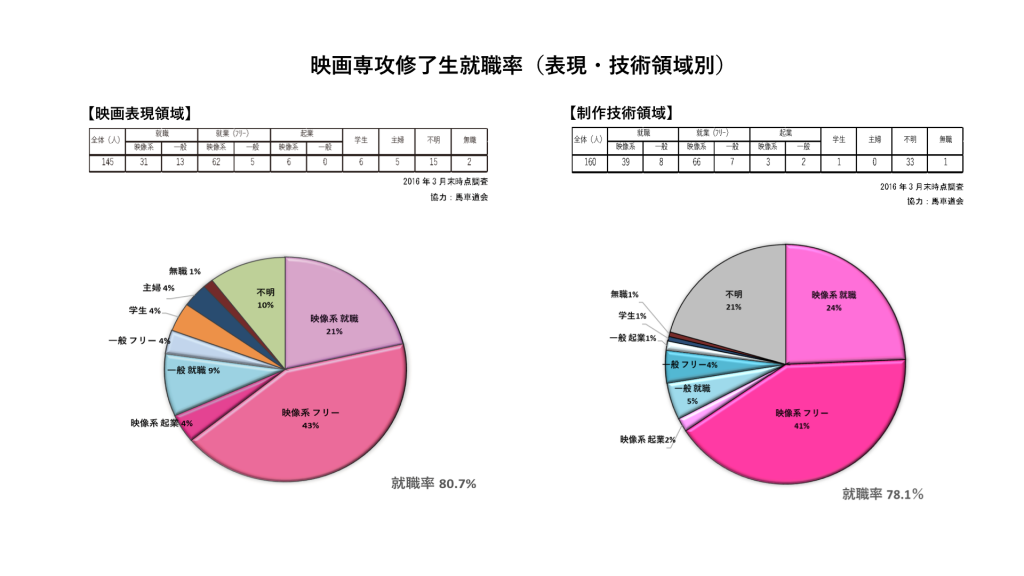世界最高峰の監督の思想に触れる
入学前は商業映画の助監督として大いに失敗した後で、もう自分は映画製作に関わることができないのではないかと思っていました。そんなとき、2005年の映像研究科設立および北野武さんと黒沢清さんの教授就任のニュースを聞いて「自分が映画製作を続けるとしたらもうこれ以外に道がない」ような切羽詰まった気持ちで受験しました。1年目で落ちても諦めきれずに2年目でようやく監督領域に合格しました。
入学当初は、何かを新たに教わろうという気持ちのない傲慢な学生だった気がします。制作実習が2年間のほとんどを占めるとは聞いていたので、最後の卒業制作に向けて自分の手法に磨きをかけていこう、ということだけ考えていました。ただ期せずして大いに学んでしまったというのが実際です。
監督領域の授業では、黒沢清教授のゼミがあって、実習の悩みやら最近見た映画の感想やら四方山話をしながらも、黒沢教授の映画作りの核心にふと触れるような瞬間がありました。それは世界最高峰の監督の思想にじかに触れるということであって、今思い返してもこの上なく贅沢な時間でした。結果的に自分の映画観を根本的に変えられてしまうような体験でした。そう思うと、映像研究科で学んだことすべてが、現在につながっている気がします。監督の仕事の根本は「どこにカメラを据え」「いつスタートとカットをかけるか」であるという認識は黒沢教授の講義やゼミから得たものです。実際の制作面においても、今組んでいるスタッフの多くはこのときに出会った人たちです。映画専攻は当時から、小さな撮影所のようであって「信頼関係」という容易には得られないものをごく自然と育ててくれました。
既に映像研究科を修了して10年近くが経過してますが、今も変わらず映画製作に心身ともに没頭できる最高の環境が用意されていることを確信しています。実体験からアドバイスすることがあるとすれば、入学希望者に対してはこの環境の有り難さは、現場で一度大きな失敗をしてから来た方がずっと身に沁みる、ということです。入学生に対しては、ここへは誰しもが自分のやりたいことがあってきているということを理解すべき、ということです。各々のやりたいことは一致しない時もあるでしょうが、コミュニケーションを重ねてその一致点を求めたら、作品は今想像しているよりずっと多くの広がりを持って受け入れられるはずです。今からここで学べる人たちを羨ましく思います。
入学当初は、何かを新たに教わろうという気持ちのない傲慢な学生だった気がします。制作実習が2年間のほとんどを占めるとは聞いていたので、最後の卒業制作に向けて自分の手法に磨きをかけていこう、ということだけ考えていました。ただ期せずして大いに学んでしまったというのが実際です。
監督領域の授業では、黒沢清教授のゼミがあって、実習の悩みやら最近見た映画の感想やら四方山話をしながらも、黒沢教授の映画作りの核心にふと触れるような瞬間がありました。それは世界最高峰の監督の思想にじかに触れるということであって、今思い返してもこの上なく贅沢な時間でした。結果的に自分の映画観を根本的に変えられてしまうような体験でした。そう思うと、映像研究科で学んだことすべてが、現在につながっている気がします。監督の仕事の根本は「どこにカメラを据え」「いつスタートとカットをかけるか」であるという認識は黒沢教授の講義やゼミから得たものです。実際の制作面においても、今組んでいるスタッフの多くはこのときに出会った人たちです。映画専攻は当時から、小さな撮影所のようであって「信頼関係」という容易には得られないものをごく自然と育ててくれました。
既に映像研究科を修了して10年近くが経過してますが、今も変わらず映画製作に心身ともに没頭できる最高の環境が用意されていることを確信しています。実体験からアドバイスすることがあるとすれば、入学希望者に対してはこの環境の有り難さは、現場で一度大きな失敗をしてから来た方がずっと身に沁みる、ということです。入学生に対しては、ここへは誰しもが自分のやりたいことがあってきているということを理解すべき、ということです。各々のやりたいことは一致しない時もあるでしょうが、コミュニケーションを重ねてその一致点を求めたら、作品は今想像しているよりずっと多くの広がりを持って受け入れられるはずです。今からここで学べる人たちを羨ましく思います。
- 監督領域 二期 濱口竜介
- 1978年生。東京芸術大学大学院映像研究科の修了作品『PASSION』('08)が国内外の映画祭で高い評価を受ける。その後も精力的な活動を続け、神戸を拠点に制作した『ハッピーアワー』(’15)はロカルノ国際映画祭で最優秀女優賞、ナント国際映画祭準グランプリ、シンガポール国際映画祭で監督賞を受賞した。